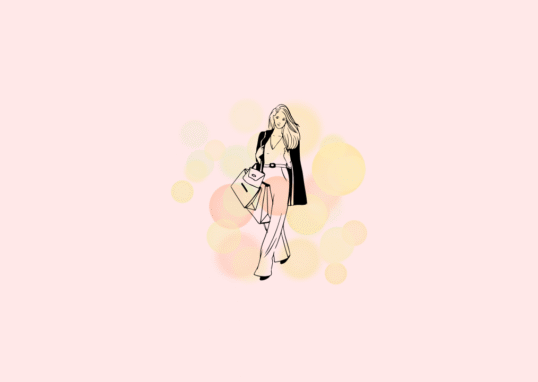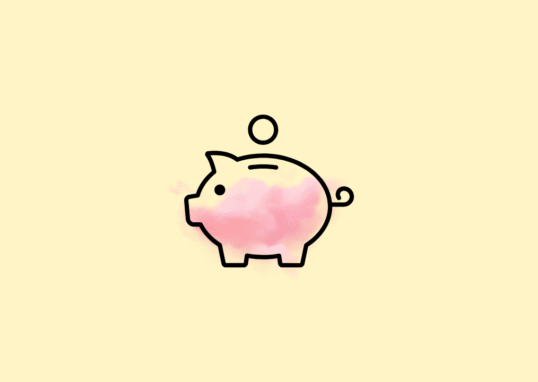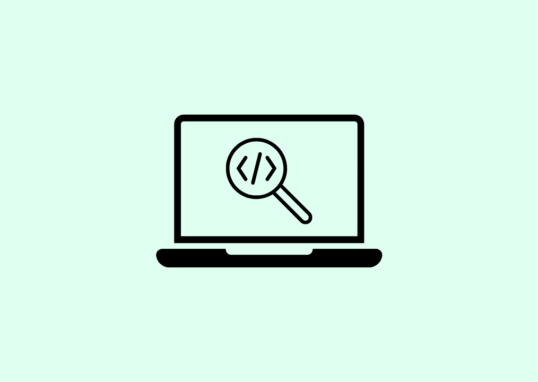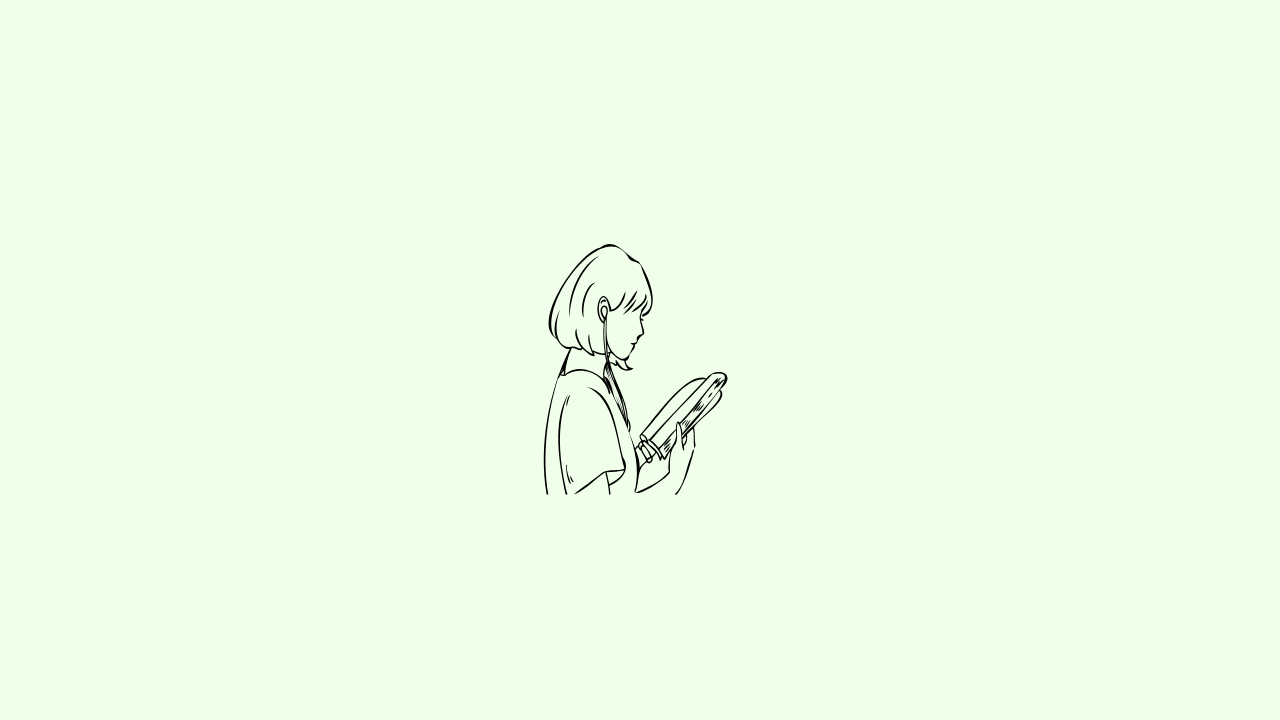
高校生までの私:勉強は嫌いだった
学生の頃の私は、勉強が嫌いでした。
「なんのためにやっているのか分からない」
「めんどくさいし、つまらない」
そんな思いを抱えながら、授業を受け、テストを受けていました。
特に親がテストの結果に厳しくなかったこともあり、悪い点を取っても叱られることはありませんでした。周囲の友達が必死に勉強している姿を見て、「どうしてそんなに頑張るんだろう?」と疑問に思うことさえありました。
転機は大学生のころ:楽しい学びとの出会い
大学進学を決めたのは、周囲の影響が大きかったと思います。私の周りには大学に進む人が多く、「なんとなく」私も大学に行くことを選びました。そして、経営学部へ進学。そこで、私は 会計学 という分野に出会います。
授業の中で、実際の企業の決算書を分析する機会がありました。その時、「企業ってこういう視点で見ると面白いんだ」と気づいたのです。さらに、1年生からインターンシップに参加し、社会人の方と話す機会を得ました。そこで、仕事の進め方や企業の構造などを学ぶことができ、興味がどんどん湧いていきました。
「もっと知りたい!」「もっと分析したい!」という気持ちが自然と湧き、気づけば勉強に夢中になっていました。初めて徹夜してレポートを書いたときも、大変という感覚より、「楽しさ」が勝っていました。大学の授業はすべて面白く、学びが苦痛ではなくなっていたのです。
就職活動とIT業界への道
大学3年生になると、就職活動が始まりました。そこで、「どんな仕事に就くのか?」と真剣に考えるようになります。私は、 結婚や出産をしても働き続けられる仕事がしたい という思いがありました。そのためには、 手に職をつけることが重要 だと感じていました。
そこで目を向けたのが IT業界 です。
もともと、小学生の頃から家のパソコンをよく触っていたこともあり、ITは好きな分野でした。そして、大学でも経営学部ながらITの専門コースを選ぶかどうかも、最後の最後まで悩んでいました。さらに、インターンシップを通じて、企業の課題をシステムで解決する仕事に興味を持つようになります。
「お客様の要望を引き出し、それを形にする仕事」
これこそが システムエンジニア(SE) の仕事でした。私は、この仕事に強く惹かれ、SEとして働くことを決意。大学3年生の3月、第一希望の企業から内定をいただきました。
コロナ禍とIT学習の日々
大学4年生になり、「最後の1年は遊ぶぞ!」と思っていた矢先、コロナの緊急事態宣言が発令されました。外に出ることが制限され、大学生活は大きく変わりました。
そこで私は、 ITの勉強に全力を注ぐ ことにしました。
大学3年間、毎日勉強する習慣がついていたので、自然とIT学習に時間を費やすようになります。毎日新しい知識と向き合い、試行錯誤の連続でした。
「分からないことと戦う日々」
この経験が、社会人になった今、大きな財産となっています。
社会人になって気づいたこと
社会人になって、学んできたことが仕事に役立つ場面が何度もありました。
例えば、
- 先輩が話している内容が理解できる瞬間
- 自分が勉強してきた知識を評価してもらえる機会
「学んだことが実際に活きる」 この実感が、勉強に対するモチベーションをさらに高めてくれました。
なぜ、勉強するようになったのか?
学生時代は赤点を取っても何も感じなかったのに、今は毎日のように学び続けています。その理由は、 学ぶことで世界の見え方が変わるから だと思います。
現在、私は データ分析の業界 で働いています。
毎日気になることが尽きず、仕事で扱った商品を自分でも買って試してみたり、休日には気になったスーパーへ足を運んだりしています。こうして、「社会って面白い!」と実感するようになったのです。
苦手だった勉強も、「こんなところで役に立つんだ!」と知ったとき、自然と学び直したくなります。知識を増やすことで、より多くのことが見えるようになり、世界がさらに面白くなるのです。
学び続ける理由
これからも、私は学び続けます。
もっと社会の仕組みを知りたい。
もっと自分の周りを「面白い」でいっぱいにしたい。
社会人になってから始まった “知的好奇心”
これは、きっとこれからも私の人生を豊かにしてくれるはずです。